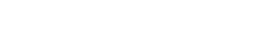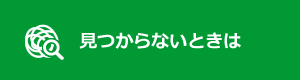国民健康保険税
病気やけがに備えて加入者が保険税を納めることで助け合う制度です。納めていただく保険税は医療費に充てるための大切な財源です。国民健康保険税は納期限内に納めてください。
納税義務者
納税義務者は世帯主となります。
世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、その世帯内に加入者がいれば世帯主に課税されます。
税額の計算方法
国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援分、介護分(40歳以上65歳未満の加入者)で構成され、それぞれに所得割、均等割、平等割の合計で計算されます。
・所得割 … (被保険者それぞれの前年中所得金額-430,000円)×税率
・均等割 … 被保険者数×税額
・平等割 … 1世帯にかかる税額
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.7% | 33,100円 | 21,400円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援分 | 2.8% | 11,900円 | 7,700円 | 260,000円 |
| 介護分(40歳~64歳) | 2.4% | 12,000円 | 5,900円 | 170,000円 |
国民健康保険税=基礎課税額【医療給付費分】+後期高齢者支援金等課税額【後期高齢者支援金等分】+介護納付金課税額【介護納付金分】
- 【医療給付費分】…医療給付費にあてるための保険税(加入者全員)
- 【後期高齢者支援金等分】…後期高齢者医療制度に必要な費用、療養病床を老健施設等に転換させる事業の費用にあてるための保険税(加入者全員)
- 【介護納付金分】…40歳から65歳未満の方が介護保険制度の運営にあてるために負担するもの
国民健康保険税の軽減
前年中の世帯の総所得が一定の基準以下の場合,均等割額及び平等割額を軽減します。
※所得未申告者がいる世帯には軽減を行うことができません。
| 軽減割合 | 軽減判定所得(世帯の合計総所得金額) |
|---|---|
| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 5割 | 43万円+30万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 2割 | 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円とし、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
※表中の{10万円×(給与所得者等の数-1)}の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ適用されます。
※賦課期日(令和7年4月1日、年度途中で加入された世帯は加入日、世帯主変更があった場合は変更があった日)現在の状況で判定します。(年度途中に加入者の増減があっても再判定されません。)
※4月1日に65歳以上になっている方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。(所得割額の計算に用いる所得額は、控除前の額を適用)
※加入者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。
※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。ただし、公的年金等に係る特別控除(15万円)後は、110万円を125万円に読み替えます。
※事業所得などがあり、かつ専従者給与を支払っている人は、所得割の計算は、専従者給与控除後の所得で行いますが、国保税の軽減判定は専従者給与控除前の所得で行います。また、専従者給与所得がある人は、所得割の計算には含めますが、軽減の判定には含めません。
※譲渡所得による特別控除がある場合は、特別控除前の額で判定します。(所得割額の計算に用いる所得額は、特別控除後の額を適用)
※法定軽減措置は、世帯の国保加入者全員と擬制世帯主及び特定同一世帯所属者が前年中の所得申告をした場合に判定されます。
自発的失業者の国民健康保険税の軽減(申請必要)
倒産・解雇などの理由により離職され、ハローワークで失業保険等を受給する手続きをされた場合は、申請により国民健康保険税が軽減されます場合があります。
(対象者)
離職日において65歳未満で雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由欄の番号が次の番号に該当する方。
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 23、33、34
(軽減内容) 失業者本人の前年の給与所得のみを30/100とみなして計算します。
(軽減期間) 離職日の翌日の属する月からその翌年度末まで。
(申請に必要なもの)
(1)印鑑 (2)雇用保険受給資格者証 (3)世帯主及び対象者の身分証明書
旧被扶養者(申請必要)
高齢者医療制度(75歳以上)の創設に伴い、会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請に基づき減免を受けることができます。
旧被扶養者については、国民健康保険税の均等割額と平等割額が5割軽減されます。加えて所得割額については全額減免となります。(ただし、既に低所得による7割・5割の軽減を受けている場合を除きます。)
※平等割額は、世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は減免対象外。
※2割軽減世帯は、2割軽減と3割減免の合計5割を減額します。
※期間は、2年経過するまで、所得割減免は2年経過しても当分の間は続きます。
(申請に必要なもの)
被用者保険の保険者が発行した、「資格喪失証明書」(被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入したことで、被扶養者の資格を喪失したことが明記されているもの)
産前産後にかかる国民健康保険税軽減について(申請必要)
(対象者)
令和5年11月1日以降に出産する(した)国保の被保険者
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)
(軽減内容)
出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間の国保税が減額されます。なお、多胎妊娠の場合は出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間の国保税が減額されます。
|
|
3か月前 |
前々月 |
前月 |
出産 |
翌月 |
翌々月 |
|
単胎妊娠 |
× |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
多胎妊娠 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
※既に課税限度額に達している世帯は減額にならない場合があります。
※免除対象月は令和6年1月からとなります(令和6年1月より前の期間については対象外です)
(例)令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月相当分のみの保険税を減額
(申請に必要なもの)
母子健康手帳など(出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。)
特定世帯(申請不要)
国保被保険者であった方が、後期高齢者(75歳以上)に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯
※国民健康保険税の「医療分」と「後期高齢支援分」の平等割額が最大で5年間は半額となり、その後は最大3年間、4分の1軽減されます。
未就学児にかかる軽減について(申請不要)
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から、未就学児の国民健康保険税の均等割額について2分の1が軽減されます。
また、均等割額は、世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がされています。(7・5・2割軽減)
この措置は、未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額するものです。
例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割の減額措置となります。
(対象者)
6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である国民健康保険被保険者(未就学児)が属する世帯の国民健康保険税納税義務者
国民健康保険税の納め方
特別徴収
下記の条件をすべて満たす世帯主の受給する年金から国民健康保険税を徴収します。
・世帯主が国民健康保険に加入者している。
・世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上75歳未満である。
・この年度中に世帯主が75歳に達しないこと。
・世帯主の特別徴収対象となる年金が年額18万円以上である。
・介護保険料が特別徴収されている。
・国民健康保険税と介護保険料の合計額が特別徴収対象となる年金額の2分の1を超えない。
※これらの条件を満たしていても年度途中の加入者等の異動により,普通徴収になる場合があります。
普通徴収(納付書・口座振替)
・町から送付された納付書により,指定された金融機関またはコンビニエンスストアで納期限内に納めてください。
・金融機関の口座より引き落としを希望される方は,あらかじめ指定された金融機関の窓口での申し込みが必要です。
| 納期 |
納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 6月2日 |
| 第2期 | 6月30日 |
| 第3期 | 7月31日 |
| 第4期 | 9月1日 |
| 第5期 | 9月30日 |
| 第6期 | 10月31日 |
| 第7期 | 12月1日 |
| 第8期 | 12月25日 |
※納期限の日が土、日、祝祭日にあたる時は、その翌日が納期限となります。